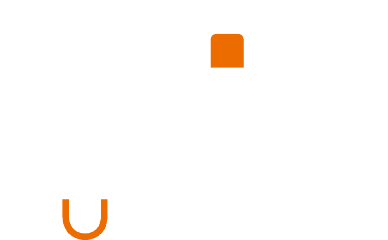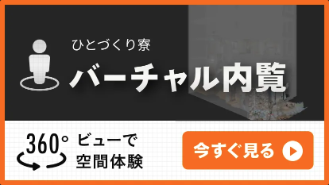社員の定着率は、企業の生産性や組織力に大きな影響を与える重要な指標です。せっかく時間とコストをかけて採用した社員が、短期間で退職してしまうと、人材育成の手間や再採用の費用がかさむだけでなく、社内の士気や企業イメージの低下にもつながりかねません。
この記事では、社員の離職率・退職率の基本的な意味から、人材が定着しない主な原因、定着率向上に成功した企業の事例までを分かりやすく解説します。また、定着率改善に貢献する新しい社員寮サービス「HuePLUS」についてもご紹介します。
社員の離職に課題を感じている採用担当者や経営者の方は、ぜひ最後までお読みいただき、自社の人材戦略の参考にしてください。
目次
社員定着とは?
社員定着とは、従業員が企業に長くとどまり、継続的に就業する状態を指します。
人材確保の観点から「リテンション(retention)」と表現されることもあり、採用後の人材をいかに社内に留め、戦力として育てられるかが重要なテーマとなっています。
社員定着のためには、以下のような要素が欠かせません。
- 自社で力を発揮できる人材を採用すること
- 早期離職を防ぐための制度や職場環境の整備
- 長期的な信頼関係を築ける労働条件やキャリア支援
こうした取り組みによって、社員のパフォーマンス向上やモチベーション維持、さらには採用や教育にかかるコストの削減にもつながります。
定着率の高い組織は、持続可能な成長と競争優位の確保にも直結するのです。
社員の定着率と離職率
従業員の定着率とは、入社した社員が一定期間内にどれだけ職場に留まっているかを示す割合です。
在籍期間が長くなるほど定着率は高くなり、働きやすさや職場環境の良し悪しを示す指標として活用されます。
定着率の基本的な計算方法は以下の通りです。

たとえば、入社時に100人いた従業員が、現在は80人になっている場合、定着率は「80 ÷ 100 × 100 = 80%」と計算されます。
ただし、より正確に定着率を出すには、計測期間中に途中入社した社員を除外する必要があります。そのため、次のような算出方法が適しています。
たとえば、過去5年間の定着状況を確認する場合、5年前に入社した社員が100人いて、そのうち30人が離職していたとします。この場合の定着率は「(100 − 30)÷ 100 × 100 = 70%」となります。
このように、定着率は対象とする期間や条件によって異なるため、評価する際には前提条件を明確にすることが大切です。
社員の離職率とは?
一方で、社員の離職率とは、一定期間内にどれだけの社員が企業を辞めたかを示す割合のことです。
一般的には「年間離職率」が用いられ、 以下の計算式で算出されます。
例えば、年間で10人が退職し、 平均従業員数が100人であれば、 離職率は10%になります。
この数値は企業の労働環境や人材マネジメントの健全性を測る一つの指標とされており、 特に近年では 「人材の定着」が重視される傾向が強まっています。
退職率との違い
「離職率」 と 「退職率」 は混同されがちですが、微妙に意味が異なります。
- 離職率は、すべての離職 (退職・契約満了解雇など) を含む広義の指標
- 退職率は、 自己都合による退職を中心とした狭義の指標
どちらも人材の流出状況を把握するために重要な数値ですが、 企業の課題をより明確にするには、それぞれを区別して分析することが大切です。
【現状】日本における離職率について
厚生労働省が公表した「令和4年 雇用動向調査」によれば、令和4年度の入職率は15.2%、離職率は15.0%で、わずかに入職者が上回る結果となりました。
この15年間の推移を振り返ると、令和2年度には新型コロナウイルスの影響により離職が入職を上回りましたが、その翌年には入職超過へと転換。令和3年度の入職率は14.0%でしたが、令和4年度には1.2ポイント上昇し15.2%となりました。
同様に、離職率も13.9%から15.0%へと上昇しており、コロナ禍の余波がうかがえます。
※出典:厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果の概要(入職と離職の推移)」
離職率が高い企業の特徴とその理由

ここからは、企業に社員が定着しない理由を解説します。
社内コミュニケーションが希薄
社員の定着率が低い企業では、社内のコミュニケーション不足がしばしば見られます。部署間の連携が取れていなかったり、上司と部下の対話が形式的であったりすると、社員は孤独感や疎外感を抱きやすくなります。
このような環境では、問題が表面化する前に退職という選択が取られるケースも少なくありません。
良好な人間関係が構築されていない
「人間関係が原因で会社を辞めた」という声は、退職理由の上位に常に挙げられます。職場で信頼できる仲間や相談できる先輩がいないと、ちょっとしたトラブルやストレスでも耐えきれなくなってしまいます。
特に新入社員や若手社員にとって、安心して話せる人間関係があるかどうかは、長期的な定着を左右する大きな要因です。
給与が適切ではない
どれほどやりがいや成長機会があっても、給与が市場水準に見合っていない、または昇給が見込めない環境では、優秀な人材ほど離職のリスクが高まります。
給与は生活の基盤であると同時に、企業からの評価や期待の表れでもあります。公平性や透明性のある報酬制度を整備することが、社員定着の基盤づくりにつながります。
労働環境が悪い
過重労働、休日出勤、長時間残業などの劣悪な労働環境は、社員の健康や精神的安定を脅かします。短期的には業績に貢献しても、長期的には人材流出と企業イメージの悪化を招くリスクがあります。
働きやすさを追求し、柔軟な勤務体系や福利厚生の充実を図ることが定着率向上に直結します。
仕事にやりがいを感じられない
自分の仕事が社会や会社にどのような影響を与えているのかが分からないと、働く意義を見失いがちです。単純作業や指示待ちの業務だけでは、モチベーションが続きません。
「自分の仕事が誰の役に立っているのか」「どんな成果が評価されるのか」を伝えることで、やりがいのある職場づくりが実現します。
しっかりと評価されない
努力や成果が適切に評価されない場合、「頑張っても無駄だ」という思いが芽生えます。評価制度が曖昧だったり、上司の主観で評価が左右されるような体制では、不満が溜まり、最終的には離職につながります。
明確な評価基準とフィードバックの仕組みを整えることが、定着率向上のカギとなります。
社員の離職率を下げ、定着率を上げる方法
社員の離職率を下げ、定着率を高めるには「なぜ離職が起きているのか」を正確に把握し、原因に応じた対策を講じることが不可欠です。以下では、代表的な改善策を紹介します。
労働環境の見直しと働き方の柔軟性
長時間労働や慢性的な残業が常態化している職場では、心身の負担が蓄積されやすく、離職につながるリスクが高まります。
まずは勤怠管理の徹底を行い、残業の上限を設定する、ノー残業デーを設けるなど、制度面からの改善が求められます。
また、業務効率化に向けたITツールの活用や、 電子化による作業時間の削減も離職率を下げるために効果的です。
加えて、在宅勤務やフレックス制度など、柔軟な勤務形態を導入することも、定着率向上に寄与します。家庭の事情やライフスタイルに応じて働き方を選べる環境があると、離職をしようと思わなくなるでしょう。
人事評価制度の透明化と整備
評価制度に対する不信感は、労働条件以上にモチベーション低下の原因となることがあります。評価基準が不明確で、年功や主観的な判断が介在する制度では、納得感が得られません。
適正な人事評価を実現するには、成果と貢献度が公平に評価される仕組みづくりが不可欠です。
たとえば「360度評価」のように、上司だけでなく同僚や部下など複数の視点から評価を行うことで、偏りの少ない客観的な評価が可能になります。
社内コミュニケーションの活性化
職場内の人間関係は、社員の定着に直結する重要な要素です。人間関係のストレスが離職理由になるケースも多く、社内のコミュニケーション施策は欠かせません。
社内報やチャットツールの活用、リフレッシュスペースの整備、部署横断型のイベントなど、自然な交流を生み出す仕組みをつくることで、離職率の低下を図れるでしょう。
教育制度とキャリア支援の強化
社員が成長を実感できない職場では、将来への不安が募り、離職のリスクが高まります。そのため、スキルアップやキャリア形成を支援する教育制度の整備が重要です。
OJTや集合研修に加え、eラーニングや外部セミナーへの参加支援、資格取得補助など、学ぶ機会を多面的に提供しましょう。
さらに、明確なキャリアパスを設定し、どのような経験やスキルを積めばステップアップできるのかを可視化することで、社員の成長意欲を後押しできます。
エンゲージメントを高める組織づくり
定着率を上げるうえで欠かせないのが、従業員エンゲージメントの向上です。エンゲージメントとは、社員が企業に信頼と愛着を持ち、自ら貢献したいと思う気持ちのことです。
これを高めるためには、企業理念やビジョンを社内にしっかりと浸透させる必要があります。
トップ層が定期的に理念を語る機会を設けたり、社内報や研修などで継続的に共有することで、一人ひとりの行動と企業の方向性を一致させやすくなり、離職率を下げる効果が見込めます。
配属・キャリア選択に柔軟性を持たせる
キャリアや配属の決定を企業側の一方的な判断で行うのではなく、社員の希望を反映する仕組みも重要です。
たとえば社内公募制度や自己申告制度、社内FA制度などを導入することで、社員が自分に合ったキャリアを主体的に選択できるようになります。
実際に、こうした柔軟な人事制度を取り入れた企業では、離職率の大幅な改善が報告されています。社員の適性や志向を尊重することが、定着率向上に直結します。
採用の質を高め、ミスマッチを防ぐ
離職率の高さは、採用段階でのミスマッチが一因であることも少なくありません。自社の社風や業務内容に適した人材を見極めるためには、要件定義の見直しが必要です。
たとえば「自社に定着している社員」の特徴を分析し、それに近い傾向を持つ応募者を選定する手法も有効です。
採用時点でのフィルタリング精度を上げることで、入社後のミスマッチを減らし、結果的に離職率を下げることが期待できます。
社員の人材定着率100%を達成した社員寮導入事例

三和建設では、ひとづくり寮の導入で「社員定着率100%」という成果を実現しました。その背景には、以下のような取り組みがあります。
コミュニケーションが促進され社員同士の仲が深まる
必要以上に部屋にこもらないように、個室のスペースは最低限に設計し、社員同士が業務外でも自然に交流でき、同期の頑張りや、悩みなども自然と相談できる関係づくりを構築できた。
最長で5年目までは入居が可能としたことで、先輩社員にも気軽に相談できることで、スピーディーな問題解決や企業文化が浸透されやすくなった。
特に若手社員にとっては、相談しやすい雰囲気や上司との距離感の近さが心理的安全性を高め、安心して働き続けられる理由となっています。
企業の理念や文化が浸透する
社員が同じ方向を向いて働くためには、企業の理念や文化の浸透が欠かせません。定期的に経営層からビジョンを共有する場を設けたり、新人研修の中で価値観教育を行うことで、会社に対する共感と愛着が生まれます。
理念の共有があることで、社員は「ただ働いている」以上の意味を見いだし、定着率の向上につながります。
離職率の改善に貢献する社員寮「HuePLUS」
「HuePLUS」は、社員の定着支援に特化した新しい形の社員寮サービスです。単に住居を提供するだけでなく、コミュニケーションの促進や心理的安全性の向上に貢献する設計が特徴です。
HuePLUSの主な特長:
- 同世代の社員と自然に関係が築ける共同生活スタイル
- プライベート空間と共用空間のバランスが取れた設計でストレスを軽減
- 地方出身者や新入社員が感じがちな「孤独」や「疎外感」を解消
- 入居者同士のつながりを活かし、社内コミュニケーションの土台づくりに貢献
実際にHuePLUSを導入した企業では、新卒社員の定着率が大幅に改善されたという実績もあります。
社員の定着率向上に課題を抱える企業にとって、HuePLUSは人材戦略の一環として検討すべき有効な手段といえるでしょう。